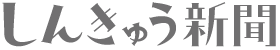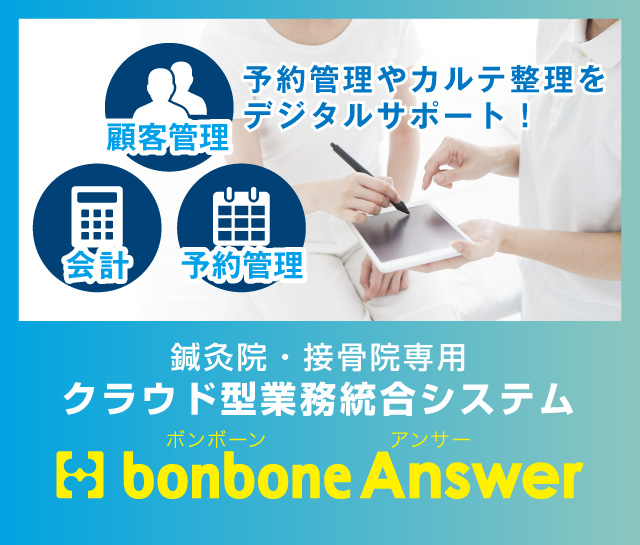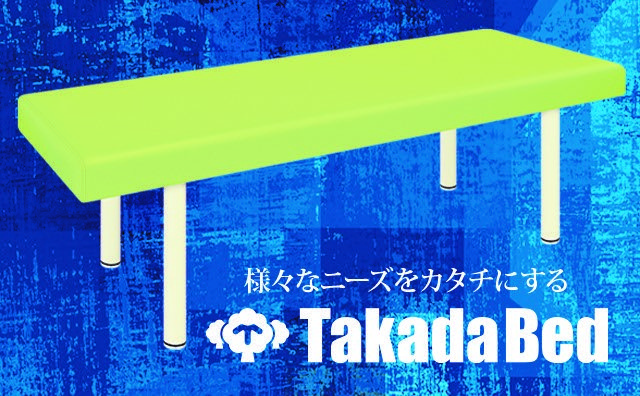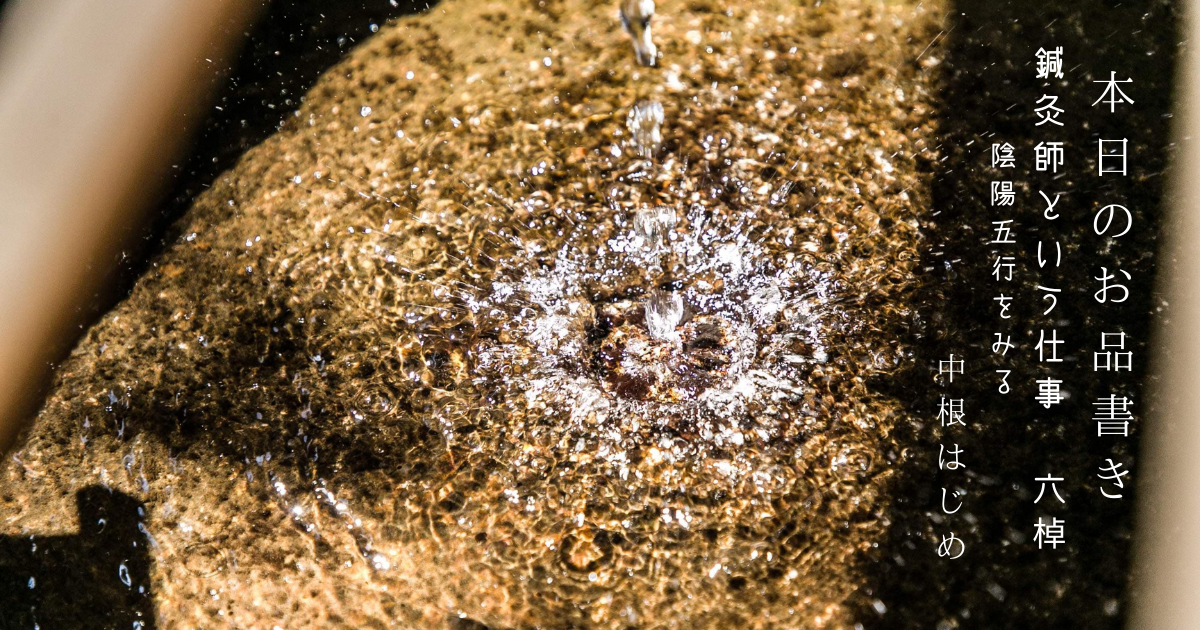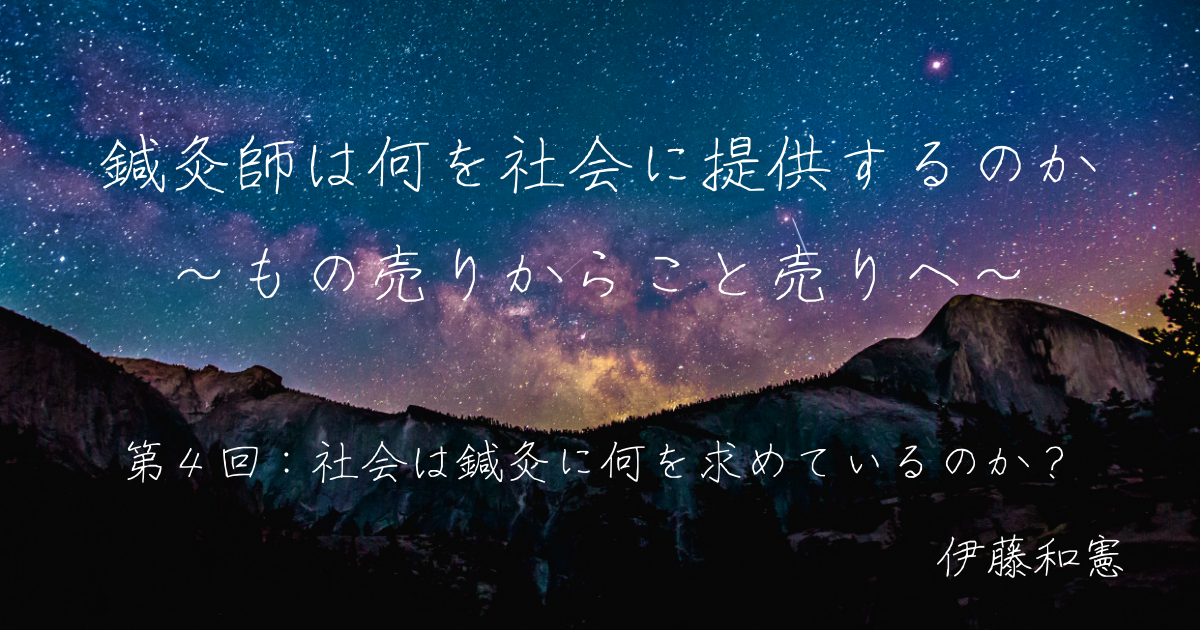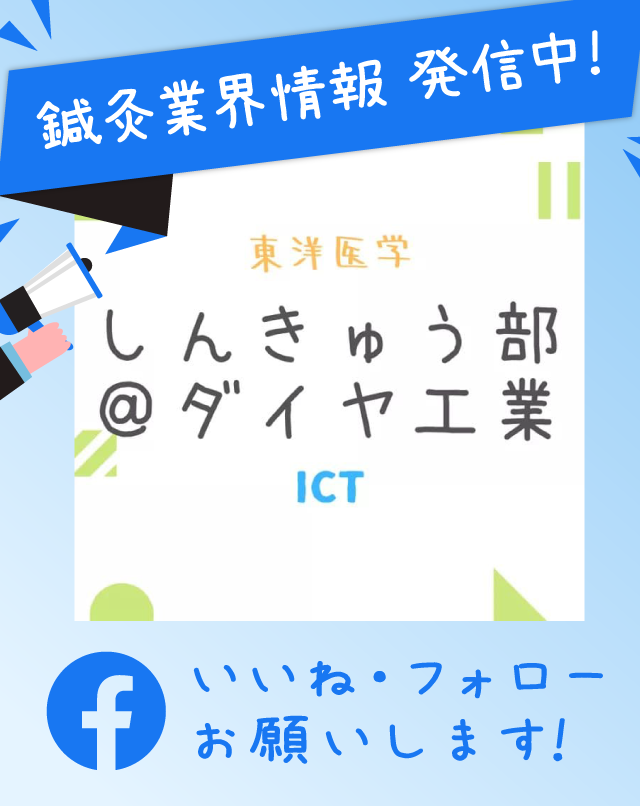鍼灸師はICTをどのように活用すべきか? ~令和時代に生きる鍼灸師のIT戦略~
更新日:2020/08/20
第4回:ICT連携で見えてくる鍼灸治療の可能性
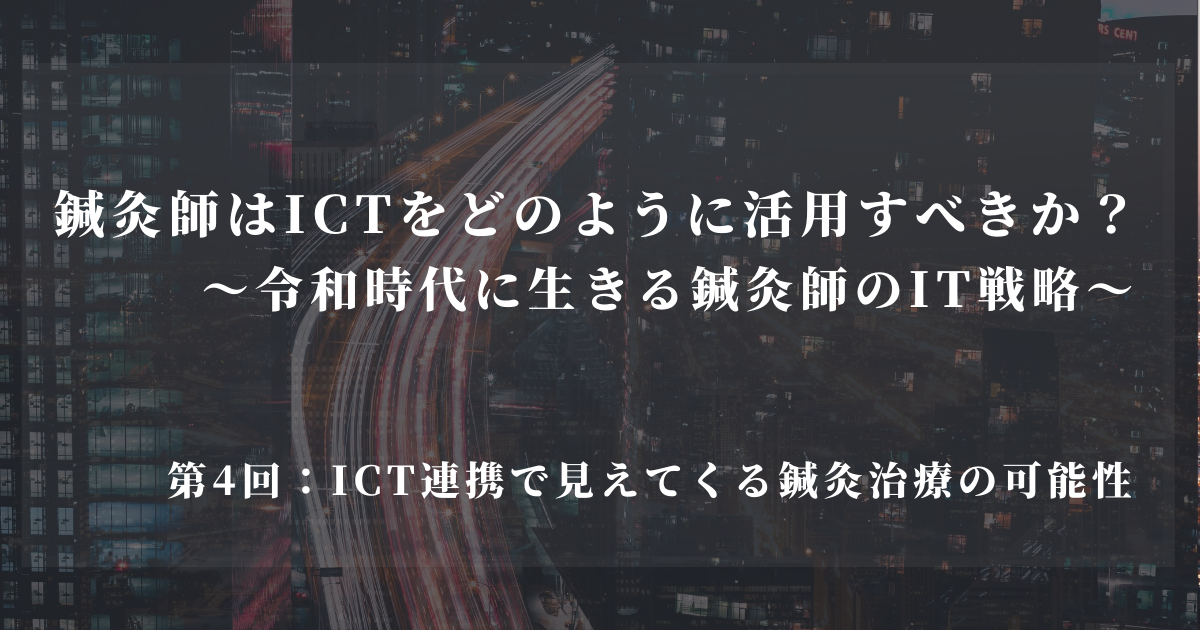
今回の連載では、鍼灸治療のIT戦略として、電子カルテ、ウエアラブルデバイス、オンライン配信などについて考えてきました。第4回目となる本記事では、鍼灸治療のICT化のメリットについてもう少し深掘りするとともに、私たちがすでに取り組んでいる実例についてお話しようと思います。
ICT化することで、自分たちの情報と他人の情報を交換、すなわち情報の一元化・共有化が進みます。そして自分達が持つ情報が他人に欲しいと思われれば思われるほど、その「見返り」として他の情報が手に入りやすくなり、そのインタラクティブな関係が活発化すれば、情報コミュニティが生まれます。5Gの時代では、低遅延かつ多接続できることから、ウエアラブルデバイスなどで得られる生活履歴(ログ)がリアルタイムで得られます。これをすでに蓄積されたweb上の情報と掛け合わせることで、新しい評価基準が生まれ診察や診断の精度が確実に上がります。そして、こうして得られた新しい情報をさらに蓄積しビックデータ化することで1つのエビデンスができます。このようにして情報の価値が高まっていくと、それを欲しがるユーザーがさらに増え、情報に経済価値が生まれます。
ここまでお話したことを整理すると、鍼灸治療がICT化することで、①我々が持っていなかった新しい情報を得ることができる、②様々な情報を掛け合わせることで診察や診断の精度が上がる、③データが集約されることで、さらなる新しい情報が生まれる、④ビックデータ化することで経済効果を生むという多くのメリットが考えられています。
一方、新型コロナウイルスにより、直接人と会うことに抵抗を持ち始めた時代にあって、ウェブを利用して、直接会わずに問題を解決しようとする動きが急速に活発化しました。実際すでにオンライン上で様々な健康相談や診察、さらには簡単な治療が行われ始めています。このような現状を鑑みると、鍼灸治療のICT化には、⑤新しい時代の診療スタイルを確立する可能性があることも、自明のことと思われます。
さてこうした可能性を前にして、実は我々も将来を見据えた新しい診療スタイルを模索しています。すでに、患者の体調把握をする「YOMOGI」というWebアプリと、「YOMOGI」の結果にプラスαの専門情報を加える「YOMOGI Pro」という姉妹アプリを開発しました。そして、この二つのアプリを用いることで、その人に合ったセルフケアの方針が決められるシステムも既に開発しており、施術者を介さなくても自動的に体調管理ができる仕組みを構築しています。これにより、体調把握からセルフケアまでの流れを簡便にすることで東洋医学を身近に感じてもらうとともに、これらのシステムを利用しても体調管理がうまく行かない人たちを専門家である鍼灸師に送客し、診療してもらえる形を作っています。そして、得られた情報を元にアプリの診断精度を高めることで医療的価値を高めたり、今後必要となるセルフケアグッズやコンテンツの開発の分析に役立てることで、企業とネットワーク形成を進めているのです。
鍼灸治療のICT化は、従来の鍼灸治療とは異なる新しい枠組みを形成する可能性を含んでいます。近年我が国はパーソナルヘルスレコード(PHR:Personal Health Record)に個人の健康・医療・介護に関する情報を集め、自己の健康状態に合った優良なサービスの提供を受けることができるシステム作りに力を入れています。そして、さらにこれらの情報に電子決済情報などの生活情報が加われば、IoTを介した快適な健康ライフが構築される可能性があります。新しい枠組みを形成する可能性を秘めた鍼灸治療のICT化。それを推し進めていくために我々鍼灸師が持つ情報をオンライン化することがとても重要です。情報を独占してしまえばネットワークコミュニティから外された閉ざされたオフラインの医療システムが、共有化すればネットワークコミュニティの一員として開かれたオープンソースの医療システムが待っています。まさに今がどちらにかじを切るかの別れ目なのです。
明治国際医療大学
伊藤和憲